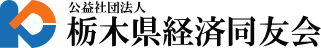筆頭代表理事のご挨拶
筆頭代表理事
藤井産業(株) 代表取締役社長
藤井 昌一
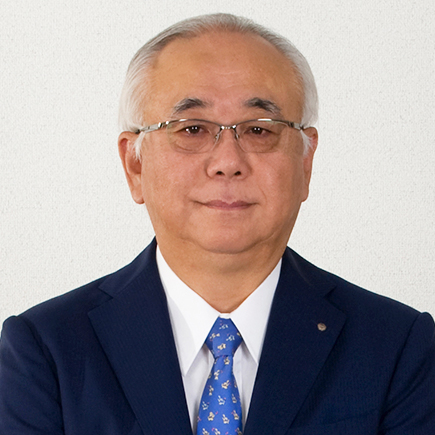
元気な「とちぎ」の創生
栃木県経済同友会は、昭和63年2月の創立以来、『郷土「栃木県」の発展と活力ある産業界の醸成に資する』という目的を達成するため、各種の政策提言や事業活動を行って参りました。
この間、平成15年4月には社団法人化し、平成24年4月からは、全国の経済同友会の中で2番目の公益社団法人として新たな一歩を踏み出しています。
本会の特色は、地元に生まれ着実に発展する中堅企業の代表者と、本県にしっかりと根を張り世界に躍進する大企業の代表者・運営責任者で構成される会員が、それぞれ個人の資格で入会し、類まれな友愛と多様性の中で活発な議論を通じて個々の資質を磨き、創造性の発揮と民間活力の発露により、栃木県の発展のために貢献するところにあります。
本会の活動の中核となる委員会事業では、地域社会が抱える様々な経済問題や社会問題について、その解決策を提言書や報告書として取りまとめ、行政や関係団体、報道機関等できるだけ多数の地域社会の人たちに訴求することにより、栃木県産業の振興と活力ある地域社会の形成を図っています。
各委員会・研究会は、令和6年度から、「生産性向上」「教育」「地方創生」のキーワードの下、それぞれ、生産性向上合同委員会(産業政策委員会・経営問題委員会・国際化推進委員会)、教育合同委員会(社会問題委員会・社会貢献活動推進委員会)、地方創生合同委員会(地域振興委員会・行財政改革委員会)として、新たなテーマで2年間の調査研究活動を行っています。
このほか、栃木県の活性化と人材育成、社会貢献事業にも力を入れ、豊かな地域社会の実現を目指しています。
本会は、公益社団法人としての使命を自覚し、更なる公益性の向上に努め、元気な「とちぎ」の創生のために引き続き積極的な活動を展開して参ります。